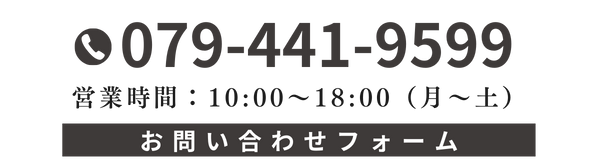建設業許可要件の営業所技術者(旧・専任技術者)の資格について施工管理技士を取り上げて詳しく解説します。
専任技術者は2024年12月に法令で名称が営業所技術者に変更になりました。
なお、2024年度(令和6年度)より、施工管理技術検定の受検資格が見直されていますので、変更点についても解説します。
建設業許可とは
建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となる国または都道府県の許可制度のことです。
建設業法に基づいて、原則として500万円以上(建築一式工事については1500万円以上または延べ面積150平方メートル以上の木造住宅)の工事を請け負う場合に建設業の許可を取得しなければなりません。
- 建設業許可の取得には、次の要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者がいること
- 営業所技術者(旧・専任技術者)が営業所ごとにいる(配置されている)こと
- 財産的基礎または金銭的信用を有していること
- 誠実性が確保されていること
- 欠格要件に該当しないこと
この中の重要な要件の一つが「専任技術者の配置」です。

営業所技術者(旧・専任技術者)とは
営業所技術者とは、建設業の許可を取得する営業所において、専らその営業所の技術的な管理を行う技術者のことです。
建設業法上、営業所ごとに少なくとも1名の営業所技術者を配置することが義務付けられており、専任であること、すなわち、ほかの営業所・支店や他社との兼務が不可という要件になっています。
営業所技術者の主な役割
- 営業所技術者の主要な役割として次のことがあります。
- 技術的な見積りや契約内容の確認
- 工事に関する顧客への技術的な説明
- 技術上の指導監督など
営業所技術者の役割は、許可された営業所で行われる建設工事において、請負契約の適正な締結及び履行を確保することになります。具体的には、上記のとおり、営業所内で見積もり作成、契約締結、発注者との技術的な打ち合わせとなっています。
営業所技術者として認められるための主な資格と実務経験
営業所技術者としての資格があることは、建設業許可を取得する上で重要になってきます。
国家資格、たとえば、施工管理技士、技術士などの取得が必要になります。国家資格がない場合は、10年以上の実務経験などの一定年数以上の実務経験が必要になります。
そのほか、指定学科の高校を卒業している場合は、5年以上の実務経験、指定学科の大学であれば3年以上の実務経験などの要件があります。

施工管理技士と営業所技術者について
施工管理技士は、建設現場における施工計画の作成、工程管理、安全管理、品質管理などを担う国家資格であり、建設業法上、営業所技術者として認められる代表的な資格の一つです。
施工管理技士には「1級」と「2級」があり、業種ごとに細かく分類されています。たとえば、土木施工管理技士、建築施工管理技士、電気工事施工管理技士などです。
- 営業所技術者として認められる施工管理技士の事例は次の資格などがあります。
- 土木工事業であれば、1級または2級土木施工管理技士
- 建築工事業であれば、1級または2級建築施工管理技士
- 電気工事業であれば、1級または2級電気工事施工管理技士
- 管工事業であれば、1級または2級管工事施工管理技士
施工管理技士の1級と2級では、担当できる工事の規模と責任の範囲が異なってきます。1級は、大規模な工事や公共工事、特定建設業の営業所技術者や監理技術者として、幅広い現場で活躍できます。
2級は、一般建設業の営業所技術者や主任技術者として、中小規模の現場を担当します。
特定建設業とは、発注者から直接請け負った工事で、下請けに出す金額が4500万円(建築一式工事の場合は7000万円)以上の場合に必要となる建設業許可です。これは、元請業者として大規模な工事を請け負い、下請け業者に工事の一部を委託する場合に必要になる許可です。
施工管理技術検定の受検資格の変更について
2024年度(令和6年度)より、施工管理技術検定の受検資格が見直されました。この改正は、建設業界の人材確保と若年層の参入促進を目的としており、学歴や実務経験に関する要件が緩和されています。
今回の受検資格の見直しによて、施工管理技術検定はより多くの人々に開かれた資格となり、若年層や未経験者でも早期に資格取得を目指すことが可能となって建設業界全体の技術力向上と人材確保が期待されています。
国土交通省の案内
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001707687.pdf
第一次検定(学科試験)の受検資格の変更内容
1級施工管理技術検定
改正前:指定学科の大学卒業後、一定の実務経験が必要。
改正後:19歳以上であれば、学歴や実務経験に関係なく受検可能となりました。
2級施工管理技術検定
17歳以上であれば受検可能です。従前からの変更はありません。
この改正により、若年層や未経験者でも早期に資格取得を目指すことが可能となりました。
第二次検定(実地試験)の受検資格の変更
第二次検定の受検資格も見直されて、学歴に依存しない実務経験の要件が導入されました。
1級施工管理技術検定
改正後:第一次検定合格後、一定の実務経験を有する者が受検可能となりました。
2級施工管理技術検定
改正後:第一次検定合格後、一定の実務経験を有する者が受検可能となりました。
具体的な実務経験の年数や内容については、各検定種目ごとに定められており、詳細は国土交通省の資料をご参照ください。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001707687.pdf
経過措置について
令和6年度から令和10年度までの間は、改正前の受検資格(旧受検資格)による第二次検定の受検も可能とする経過措置が設けられています。
これによって、従来の学歴や実務経験に基づく受検資格を有する方も、引き続き受検することができます。
特定実務経験の導入
新たに「特定実務経験」が導入されて、一定の規模以上の工事において、監理技術者や主任技術者の指導のもとで行った実務経験が評価されます。
国土交通省の案内より
請負金額4500万円(建築一式工事は7,000万円)以上の建設工事において、監理技術者・主任技術者(当該業種の監理技術者資格者証を有する者に限ります)の指導の下、または自ら監理技術者・主任技術者として行った経験(発注者側技術者の経験、建設業法の技術者配置に関する規定の適用を受けない工事の経験等は特定実務経験には該当しません)
これにより、より実践的な経験を積んだ技術者が評価されやすくなりました。